発酵食品がメンタルを救う?脳に効く腸内フード5選
- 健幸アンバサダー
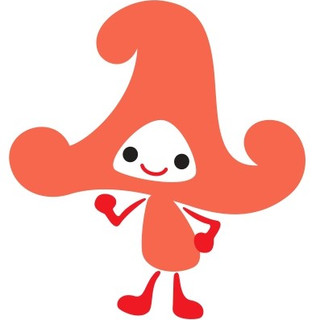
- 2025年10月13日
- 読了時間: 5分
発酵食品とメンタルの関係 腸内環境が気分を左右する理由
「発酵食品は体に良い」と耳にする機会は多いですが、実は近年、メンタルヘルスとの深い関わりが注目されています。近年の研究によると、発酵食品に含まれる乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスが腸内フローラを改善し、その変化が脳の働きや感情に影響を及ぼす可能性が示されています。

腸と脳をつなぐ「脳腸相関」とは? サイコバイオティクスの最新知見
この腸と脳の密接なつながりは「脳腸相関(gut–brain axis)」と呼ばれ、さらに精神的な健康に特に有益に働く菌を「サイコバイオティクス(psychobiotics)」と呼ぶ研究者もいます。つまり、発酵食品は“腸を通じて脳をサポートする天然のメンタルケア”として再評価されているのです。
発酵食品がメンタルに効く3つのメカニズム
発酵食品がどのようにメンタルに作用するのか、代表的に3つの仕組みが知られています。

腸内環境改善とセロトニン合成サポート
体内のセロトニンの約90%以上は腸で生成されますが、腸で作られたセロトニン自体は脳へ直接届きません。ただし、腸内細菌はセロトニンの原料であるトリプトファンの吸収や代謝を助けるため、結果的に脳内セロトニン合成に良い影響を与える可能性があります。
腸の炎症を抑えて脳も守る抗炎症作用
慢性的な腸の炎症は、全身をめぐるサイトカインを介して脳機能に悪影響を及ぼすと考えられています。発酵食品に含まれる乳酸菌には、腸内の炎症性物質を減らす作用があることが報告されています。
ストレス応答系(HPA軸)の調整で心を安定
腸内環境は、ストレス応答の要となるHPA軸(視床下部—下垂体—副腎系)に関与しています。動物実験や一部の臨床研究では、発酵食品やプロバイオティクスの摂取がストレスホルモンの過剰な分泌を抑える可能性が示されています。
脳に効くおすすめ発酵食品5選【腸活でうつ予防】
日本の食文化に根付いており、継続しやすい発酵食品を5つご紹介します。

ヨーグルト|乳酸菌とビフィズス菌で腸を整える
乳酸菌・ビフィズス菌が豊富。朝食にぴったりで、果物やはちみつを添えると栄養バランスもアップ。
納豆|納豆菌とビタミンB群で脳をサポート
納豆菌に加え、ビタミンB群やマグネシウムも含有。脳と腸の働きを支える優秀な発酵食品です。
味噌|生味噌の乳酸菌を毎日の味噌汁で
味噌汁として摂るのが一般的ですが、加熱しすぎると菌が死滅するため、仕上げに溶く“後入れ”が理想です。
キムチ|植物性乳酸菌が豊富な発酵野菜
植物性乳酸菌を多く含み、食物繊維やビタミンCも豊富。市販品は「乳酸発酵」と明記されたものを選ぶと安心です。
甘酒|オリゴ糖とアミノ酸で腸と脳を元気に
“飲む点滴”と呼ばれ、オリゴ糖や必須アミノ酸を含むため、プレバイオティクス効果も期待できます。
発酵食品を毎日続けるコツ 複数種をローテーションで取り入れる
発酵食品は体質との相性があるため、同じものを大量に摂るよりも、複数を少量ずつローテーションで取り入れるのが理想です。例えば下記のような組み合わせはいかがでしょうか。
月曜:ヨーグルト+バナナ
火曜:納豆ご飯+味噌汁
水曜:キムチ+豆腐
木曜:甘酒+グラノーラ

さらに、発酵食品の中には糖質や塩分が多いものもあります。1日1〜2品を目安に、無理なく継続するのがコツです。
発酵食品で腸と心を整える新しいセルフケア
ストレス社会で生きる私たちにとって、「食べて整えるメンタルケア」はもっとも身近で持続可能な方法です。薬やサプリに頼る前に、まずは日々の食卓から。腸と脳がつながっていることが分かってきた今だからこそ、食事がこころの土台を支えるという視点を持つことが大切です。

今日の一口の選択が、明日の気分を変える。発酵食品を上手に取り入れて、腸と心を同時にケアする新しい習慣を始めてみませんか?
健幸アンバサダー養成講座 オンライン講座のご案内
厚生労働省「健康寿命をのばそう!アワード」で優良賞を受賞したプログラムです。健康でい続けるためには正しい健康情報が不可欠です。いつでも、どこでも、受講可能なオンライン講座を是非お試しください。詳しくはこちらから。
毎日の体操があなたの未来を変える
毎日の運動の積み重ねが、心と体を大きく変えていきます。運動習慣をつけてスマートウエルネスライフを実現しましょう。
毎日の健幸維持のためオリジナル体操プログラムをつくりました。監修いただいたのは2004年アテネオリンピック体操団体金メダリストで体操競技元日本代表監督の水鳥寿思さん。アンバサダーとして健幸を維持するために、大切な人の健幸のためにも。手軽にできる体操ばかりなので是非実践してみてくださいね。健幸体操はこちらから。
出典・参考文献
厚生労働省 e-ヘルスネット「腸内細菌」
Cryan JF, et al. (2019). The Microbiota–Gut–Brain Axis. Physiol Rev, 99(4):1877–2013.
Gershon MD. (1998). The Second Brain. Harper Perennial.
Ng QX, et al. (2018). A systematic review of the role of prebiotics and probiotics in depression. Nutritional Neuroscience, 22(8):469–478.

塚尾 晶子
株式会社つくばウエルネスリサーチ 取締役副社長/筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研究センターアドバイザー/保健師
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士課程修了 博士(スポーツウエルネス学)/ 専門領域はスポーツウエルネス学、保健学、人間環境学、公衆衛生学。
旭化成株式会社での産業保健活動、日本看護協会での健康政策の厚生労働省委託事業推進や保健師現任教育、法政大学での兼任講師等を経て、現職。地方自治体、企業等のSmartWellnessCity(健康都市政策)推進のコンサルティング、人材育成、国の調査研究事業等に従事し、国や地方自 治体や大学、企業と連携して健康づくり無関心層を減少させ健康格差を和らげる政策に取り組む。









